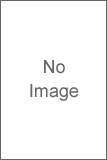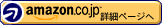『ふしぎなキリスト教 (講談社現代新書)』の読書ノート作成者:tsuzuki670 さん
2015/03/17 作成
旧約聖書の核となるのがモーセ五書。すなわち創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。
創世記にはカインとアベルの話がある。2人はアダムとイヴの息子で、カインが兄、アベルが弟である。アベルが神への捧げた供物が気に入られたことに嫉妬したカインは、アベルを殺す。その殺人はヤハウェにも暴露し、カインは追放される。アブラハム・イサク・ヤコブの三代の話。遊牧民の族長アブラハムはバビロニアからカナン(現在のイスラエル)に移動する。アブラハムは諸民族の長になるよう神から祝福を受ける。ヤコブの子ども12人がそれぞれイスラエルの12部族となる。ヤコブの末っ子のヨセフは兄たちに虐められていたがやがてエジプトの宰相にまで上り詰め、飢饉に苦しむ兄たちをエジプトへと呼び寄せて助けた。
出エジプト記。やがてエジプトの王朝が変わるとイスラエルの民は迫害を受けたので、モーセに率いられたイスラエルの民はエジプトを脱出する。エジプト軍に追われながらカナンの地を目指す彼らは、海を割る「モーセの奇跡」などを起しながら40年間シナイ半島を放浪する。その道中、シナイ山でモーセは神から十戒を授かる。
レビ記、民数記、申命記は物語よりも立法が主な内容である。申命記の最後でヨルダン川越しにカナンの地を望む場所までたどり着いたとき、モーセは後継者にヨシュアを指名して亡くなる。
ヨシュア記では、ヨシュアに率いられたイスラエル人たちはカナンの諸都市を攻略して、そこへの移住を果たす。
士師記では、ヨシュアに続く裁判官かつ軍事指導者であるデボラ、ギデオン、サムソンに率いられる時代が描かれる。
サムエル記は最後の士師であるサムエルの時代、そしてサムエルの後継者で初めて王となったサウルの時代が描かれる。ここにおいてイスラエルは部族連合体から王制国家へと移行する。サウルは戦果をあげるものの、神の意に背いたため追放される。そこでサムエルはサウルの代わりにダビデを次の王に指名する。もともと羊飼いであったダビデはまず南部のユダ王国の王となり、次いで北部のイスラエル王国の王となる。ダビデは文武に秀でた王として旧約聖書中最大の賛辞を受けている。ダビデは神が中にいるとされる「契約の箱」を作った。
列王記ではダビデの息子ソロモンの治世に王国が最盛期を迎え、栄華を極める。ソロモンは智慧に優れた王であったが、調子にのって過酷な徴税を行った結果、ダビデの時代に統一された王国は、南部のユダ王国と北部のイスラエル王国に分裂してしまう。北部のイスラエル王国はアッシリアに、南部のユダ王国は新バビロニアに滅ぼされ、このとき一万人のユダ王国の民がバビロンに捕囚される。(紀元前600年)エルサレムの神殿を破壊されたユダヤ人は立法を支えとするようになり、教義としてのユダヤ教を確立させていく。この時代にヤハウェの再解釈が行われ、ヤハウェはユダヤ民族の神であるだけでなく、人類全体の唯一神として理解されるようになった。
アケネメス朝ペルシアが新バビロニアを滅ぼしたことで、ユダヤ人はおよそ50年ぶりにパレスチナへと帰還する。パレスチナに帰還した人々はエルサレムに神殿を再建して、アケネメス朝ペルシアの支配下に入る。
旧約聖書においてバビロン捕囚以降の歴史記述は断片的にしか語られていない。
旧約聖書の三大預言者はイザヤ、エレミヤ、エゼキエルである。イザヤはユダ王国後期の人。すなわち、ソロモン王の死後に王国が南部に分裂してから、新バビロニアにユダ王国が滅ぼされるまでの間の人。エレミヤとエゼキエルはバビロン捕囚の頃の人。
1-1
キリスト教はユダヤ教を否定的な形で含みこんでいるという点で特異である。両者の違いは、神との接し方である。ユダヤ教は預言者を通じて間接的に、キリスト教はイエス・キリストという神の子という形でより直接的に神と接する。
1-2
多神教と一神教の根源的な違いは「神が人間みたいな存在か」「人間を超越した存在か」という点にある。一神教の神は人間をモノのように扱う恐ろしい存在であり、人間は「こうするから殺さないで下さい」という「契約」を結んだ。キリストはその冷徹な関係に「愛」を持ち出した点で革命的だった。
1-3
ヤハウェはもともと火山をかたどった戦争の神であり、遊牧を営むイスラエルの民に崇められる神々のひとつに過ぎなかったし、ヤハウェの偶像も造られていた。
1-4
イスラエル王国の成立において、神が王を任命するという形で王制と信仰が結びつく。その後バビロン捕囚において、①「いまは捕囚されているけどヤハウェが唯一神でユダヤ人は選ばれし民なのだ」と希望を求め、②「バビロン捕囚は神がユダヤ人に与えた試練なのだ」と合理化することを通じて、ユダヤ教は一神教としての形を確立してきた。現在のユダヤ教は律法学者中心の宗教だが、律法は未整備だったバビロン捕囚以前の時期には預言者が、神殿が中心だった時代には司祭が大きな力を持っていた。キリストは預言者の流れを汲んでいる。
1-5
ユダヤ人が連戦連敗なのに自民族を守るはずのヤハウェを信仰し続けたのはなぜか? それはみじめな現実を合理化するために、「それでも僕たちは選ばれているんだ。この惨状は一時的な試練なんだ」という「いじめられっ子の心理」に縋ったからである。
1-6
ユダヤ教の律法は、国家が滅んだとしても人々が散り散りになったとしてもユダヤ民族がユダヤ民族で在り続けられるように、という目的で作られている。
1-7
アダムとイヴが禁断の実を食べた話は原罪とは関係ない。原罪という考え方はユダヤ教にはなく、キリスト以降に現れる。現在とは、神に背く行い=「行為レベルの罪」ではなく、どう努力しても神に背くことをしがちであるという人間の生来的な性質を指す、「存在レベルの罪」である。
1-8
ユダヤ教はユダヤ人にしか信仰を許されない「ユダヤ人の神」であるが、その教義によればヤハウェはユダヤ民族以外のことも心配する「人類全体の神」である。そして「全人類のことを統括する神が、なぜユダヤ人を選んだのか」という問いに対してユダヤ人は「理由は分からないが、誇らしいことだ」と考える。「なぜ神はこれを正しいとしたのか」と問うのではなく「神がしたのだからこれは正しいことなのだ」と考え受け入れるこの姿勢は、一神教の根源的な特徴である。
1-9
「なぜ全知全能の神が造った世界に欠陥や悪があるのか?」という疑問も上記の態度によって引き受けられている。つまり、「なぜ欠陥や悪や禍いや不幸があるのか」、そのことを問い続け、神から与えられた試練として引き受け続けることこそが祈りであり信仰なのである。
1-10
「なぜ苦しまねばならぬのか」という議論は『ヨブ記』にも現れる。そこでは神は饒舌にヨブの問いに答えず、いわば神との対話不可能性が描かれている。また同時に神の理解可能性・対話可能性を想定する、ヨブの友人たちの思考は神によって否定されている。「なぜ苦しまねばならぬのか」という問いに対しては「禁断の実を食べた罰だ」という答えもあり得るが、しかしこれも「なぜ全知全能の神は禁断の実をつくって、禁断の実を食べてしまうような人間をつくって、彼らを残していったのか。神はこの事態が起きることを知っていたはずだ。なぜわざわざその事態を起したのか」という、先程と同様の問いを再び発生させるに過ぎず、やはり神との対話不可能性は残る。いずれにせよ、このような神との不可能なコミュニケーションの希求こそが祈りであり、信仰とは謂わば不合理の合理化を不断に試みる営みだと言える。
1-11
偶像崇拝の禁止は「(目に見える形で)存在しないものが、もっとも強烈な存在である」というパラドクスを含んでいる。偶像崇拝が禁止されるのは「人間が造った偶像を崇めることは、人間自身を崇めることになるから」である。
1-12
「神が人間から隔絶している」ことと「神は人間を神に似せて造った」ことは矛盾するか。橋爪の答えは「人間は神に似ているが、神は人間に似ていない」というものだ。3次元と2次元のような関係で、神をある角度から写し取ったものが人間であるが、人間の姿から神を再構成することは到底できないとすると、上記の2つの命題が矛盾なく両立する。
1-13
一神教は一般的に超部族的な帝国権力との結びつきが強いが、ユダヤ教は帝国的な権力との親和性が低い。その背景には、①アブラハムがカナンにおいて下層に位置する居留者であり「権力を持たぬ側」であったという歴史的事実と、②神と人間との圧倒的な非対称性ゆえに、神の前での人間の平等性が生じるという思想的特徴がある。(しかしこれではユダヤ教と他の一神教の違いを説明できない。)具体的な権力抑止の方法としては、①安息日を初めとする社会福祉的な諸規定、②預言者や長老による国王の任命・罷免の可能性が挙げられる。(この説明もユダヤ教と他の宗教との一神教との違いを明らかにしていない。)
1-14
預言者はその前期にはただのシャーマン的な存在だった。中期には王権に対する批判者として現れた。後期には律法学者との対立の中で「本物の預言者なのか」という懐疑に曝される存在になった。預言者という仕組みも神が設計したものだと考えるならば、預言を聴き・見極めて・信じるという営みもまた信仰の一部であり、そこにおいて信仰心が試されたと言える。また預言という営みは人間の発する言葉が神に繋がる絶対的な力を持ちうるという「言葉への信頼」を育んだ。
1-15
預言を信じる過程において、信仰はいわば神と人間の共同作業によって生み出される。この作業の中での神の側からの譲歩として、神は或る者が預言者である証拠として奇蹟を起こす。奇蹟を信じることは、超越的な神が人間には動かし得ない絶対の「科学的な」法則を定めたと信じることと表裏一体である。世界の運用のされ方が人間によっては改変されえず、常に絶対的な存在によってのみ定められ/破られるという発想において、科学と奇蹟は対立するものではなくむしろ相補的なものだ。こうした世界観に対置されるのは「人間の側からの特殊なアプローチによって世界の運用の決まりを修正しうる、神々の世界にアプローチし得る」と考える呪術の発想である。
1-16
キリスト教はもともと、聖書の全てを字義通りに正しいと信じるものではない。(より多くの表現を整合的に受けとめられるような考え方を暫定的に採用することが信仰?)科学と宗教は部分的に矛盾を来す場合があるものの、根本的には対立するものではない。「矛盾した場合にはどちらを採用する」という一定の方針のもと認識を擦り合わせれば、それらは十分に整合的なものとなる。キリスト教徒の多数派は「科学に矛盾しない限りにおいて宗教を信じる」、福音派は「宗教に矛盾しない限りにおいて科学を信じる」という態度をとる。両者はどちらに重点を置くかが異なるだけで、極めて同型的である。また信仰には、教義を事実として意識的に信じる次元と、その宗教がもつ認識の枠組みや世界への態度を無意識的に身につけ振る舞う次元とがある。
丸山眞男によれば、宇宙の起源を説明する論理には「神が宇宙を創造する」「神が宇宙を産む」「宇宙は植物のように生成する」という3つの類型がある。
キリスト教やユダヤ教において苦しみを試練と捉えるのは、仏教の一切皆苦の思想と同じ「機能」を果たしていると感じる。
創世記にはカインとアベルの話がある。2人はアダムとイヴの息子で、カインが兄、アベルが弟である。アベルが神への捧げた供物が気に入られたことに嫉妬したカインは、アベルを殺す。その殺人はヤハウェにも暴露し、カインは追放される。アブラハム・イサク・ヤコブの三代の話。遊牧民の族長アブラハムはバビロニアからカナン(現在のイスラエル)に移動する。アブラハムは諸民族の長になるよう神から祝福を受ける。ヤコブの子ども12人がそれぞれイスラエルの12部族となる。ヤコブの末っ子のヨセフは兄たちに虐められていたがやがてエジプトの宰相にまで上り詰め、飢饉に苦しむ兄たちをエジプトへと呼び寄せて助けた。
出エジプト記。やがてエジプトの王朝が変わるとイスラエルの民は迫害を受けたので、モーセに率いられたイスラエルの民はエジプトを脱出する。エジプト軍に追われながらカナンの地を目指す彼らは、海を割る「モーセの奇跡」などを起しながら40年間シナイ半島を放浪する。その道中、シナイ山でモーセは神から十戒を授かる。
レビ記、民数記、申命記は物語よりも立法が主な内容である。申命記の最後でヨルダン川越しにカナンの地を望む場所までたどり着いたとき、モーセは後継者にヨシュアを指名して亡くなる。
ヨシュア記では、ヨシュアに率いられたイスラエル人たちはカナンの諸都市を攻略して、そこへの移住を果たす。
士師記では、ヨシュアに続く裁判官かつ軍事指導者であるデボラ、ギデオン、サムソンに率いられる時代が描かれる。
サムエル記は最後の士師であるサムエルの時代、そしてサムエルの後継者で初めて王となったサウルの時代が描かれる。ここにおいてイスラエルは部族連合体から王制国家へと移行する。サウルは戦果をあげるものの、神の意に背いたため追放される。そこでサムエルはサウルの代わりにダビデを次の王に指名する。もともと羊飼いであったダビデはまず南部のユダ王国の王となり、次いで北部のイスラエル王国の王となる。ダビデは文武に秀でた王として旧約聖書中最大の賛辞を受けている。ダビデは神が中にいるとされる「契約の箱」を作った。
列王記ではダビデの息子ソロモンの治世に王国が最盛期を迎え、栄華を極める。ソロモンは智慧に優れた王であったが、調子にのって過酷な徴税を行った結果、ダビデの時代に統一された王国は、南部のユダ王国と北部のイスラエル王国に分裂してしまう。北部のイスラエル王国はアッシリアに、南部のユダ王国は新バビロニアに滅ぼされ、このとき一万人のユダ王国の民がバビロンに捕囚される。(紀元前600年)エルサレムの神殿を破壊されたユダヤ人は立法を支えとするようになり、教義としてのユダヤ教を確立させていく。この時代にヤハウェの再解釈が行われ、ヤハウェはユダヤ民族の神であるだけでなく、人類全体の唯一神として理解されるようになった。
アケネメス朝ペルシアが新バビロニアを滅ぼしたことで、ユダヤ人はおよそ50年ぶりにパレスチナへと帰還する。パレスチナに帰還した人々はエルサレムに神殿を再建して、アケネメス朝ペルシアの支配下に入る。
旧約聖書においてバビロン捕囚以降の歴史記述は断片的にしか語られていない。
旧約聖書の三大預言者はイザヤ、エレミヤ、エゼキエルである。イザヤはユダ王国後期の人。すなわち、ソロモン王の死後に王国が南部に分裂してから、新バビロニアにユダ王国が滅ぼされるまでの間の人。エレミヤとエゼキエルはバビロン捕囚の頃の人。
1-1
キリスト教はユダヤ教を否定的な形で含みこんでいるという点で特異である。両者の違いは、神との接し方である。ユダヤ教は預言者を通じて間接的に、キリスト教はイエス・キリストという神の子という形でより直接的に神と接する。
1-2
多神教と一神教の根源的な違いは「神が人間みたいな存在か」「人間を超越した存在か」という点にある。一神教の神は人間をモノのように扱う恐ろしい存在であり、人間は「こうするから殺さないで下さい」という「契約」を結んだ。キリストはその冷徹な関係に「愛」を持ち出した点で革命的だった。
1-3
ヤハウェはもともと火山をかたどった戦争の神であり、遊牧を営むイスラエルの民に崇められる神々のひとつに過ぎなかったし、ヤハウェの偶像も造られていた。
1-4
イスラエル王国の成立において、神が王を任命するという形で王制と信仰が結びつく。その後バビロン捕囚において、①「いまは捕囚されているけどヤハウェが唯一神でユダヤ人は選ばれし民なのだ」と希望を求め、②「バビロン捕囚は神がユダヤ人に与えた試練なのだ」と合理化することを通じて、ユダヤ教は一神教としての形を確立してきた。現在のユダヤ教は律法学者中心の宗教だが、律法は未整備だったバビロン捕囚以前の時期には預言者が、神殿が中心だった時代には司祭が大きな力を持っていた。キリストは預言者の流れを汲んでいる。
1-5
ユダヤ人が連戦連敗なのに自民族を守るはずのヤハウェを信仰し続けたのはなぜか? それはみじめな現実を合理化するために、「それでも僕たちは選ばれているんだ。この惨状は一時的な試練なんだ」という「いじめられっ子の心理」に縋ったからである。
1-6
ユダヤ教の律法は、国家が滅んだとしても人々が散り散りになったとしてもユダヤ民族がユダヤ民族で在り続けられるように、という目的で作られている。
1-7
アダムとイヴが禁断の実を食べた話は原罪とは関係ない。原罪という考え方はユダヤ教にはなく、キリスト以降に現れる。現在とは、神に背く行い=「行為レベルの罪」ではなく、どう努力しても神に背くことをしがちであるという人間の生来的な性質を指す、「存在レベルの罪」である。
1-8
ユダヤ教はユダヤ人にしか信仰を許されない「ユダヤ人の神」であるが、その教義によればヤハウェはユダヤ民族以外のことも心配する「人類全体の神」である。そして「全人類のことを統括する神が、なぜユダヤ人を選んだのか」という問いに対してユダヤ人は「理由は分からないが、誇らしいことだ」と考える。「なぜ神はこれを正しいとしたのか」と問うのではなく「神がしたのだからこれは正しいことなのだ」と考え受け入れるこの姿勢は、一神教の根源的な特徴である。
1-9
「なぜ全知全能の神が造った世界に欠陥や悪があるのか?」という疑問も上記の態度によって引き受けられている。つまり、「なぜ欠陥や悪や禍いや不幸があるのか」、そのことを問い続け、神から与えられた試練として引き受け続けることこそが祈りであり信仰なのである。
1-10
「なぜ苦しまねばならぬのか」という議論は『ヨブ記』にも現れる。そこでは神は饒舌にヨブの問いに答えず、いわば神との対話不可能性が描かれている。また同時に神の理解可能性・対話可能性を想定する、ヨブの友人たちの思考は神によって否定されている。「なぜ苦しまねばならぬのか」という問いに対しては「禁断の実を食べた罰だ」という答えもあり得るが、しかしこれも「なぜ全知全能の神は禁断の実をつくって、禁断の実を食べてしまうような人間をつくって、彼らを残していったのか。神はこの事態が起きることを知っていたはずだ。なぜわざわざその事態を起したのか」という、先程と同様の問いを再び発生させるに過ぎず、やはり神との対話不可能性は残る。いずれにせよ、このような神との不可能なコミュニケーションの希求こそが祈りであり、信仰とは謂わば不合理の合理化を不断に試みる営みだと言える。
1-11
偶像崇拝の禁止は「(目に見える形で)存在しないものが、もっとも強烈な存在である」というパラドクスを含んでいる。偶像崇拝が禁止されるのは「人間が造った偶像を崇めることは、人間自身を崇めることになるから」である。
1-12
「神が人間から隔絶している」ことと「神は人間を神に似せて造った」ことは矛盾するか。橋爪の答えは「人間は神に似ているが、神は人間に似ていない」というものだ。3次元と2次元のような関係で、神をある角度から写し取ったものが人間であるが、人間の姿から神を再構成することは到底できないとすると、上記の2つの命題が矛盾なく両立する。
1-13
一神教は一般的に超部族的な帝国権力との結びつきが強いが、ユダヤ教は帝国的な権力との親和性が低い。その背景には、①アブラハムがカナンにおいて下層に位置する居留者であり「権力を持たぬ側」であったという歴史的事実と、②神と人間との圧倒的な非対称性ゆえに、神の前での人間の平等性が生じるという思想的特徴がある。(しかしこれではユダヤ教と他の一神教の違いを説明できない。)具体的な権力抑止の方法としては、①安息日を初めとする社会福祉的な諸規定、②預言者や長老による国王の任命・罷免の可能性が挙げられる。(この説明もユダヤ教と他の宗教との一神教との違いを明らかにしていない。)
1-14
預言者はその前期にはただのシャーマン的な存在だった。中期には王権に対する批判者として現れた。後期には律法学者との対立の中で「本物の預言者なのか」という懐疑に曝される存在になった。預言者という仕組みも神が設計したものだと考えるならば、預言を聴き・見極めて・信じるという営みもまた信仰の一部であり、そこにおいて信仰心が試されたと言える。また預言という営みは人間の発する言葉が神に繋がる絶対的な力を持ちうるという「言葉への信頼」を育んだ。
1-15
預言を信じる過程において、信仰はいわば神と人間の共同作業によって生み出される。この作業の中での神の側からの譲歩として、神は或る者が預言者である証拠として奇蹟を起こす。奇蹟を信じることは、超越的な神が人間には動かし得ない絶対の「科学的な」法則を定めたと信じることと表裏一体である。世界の運用のされ方が人間によっては改変されえず、常に絶対的な存在によってのみ定められ/破られるという発想において、科学と奇蹟は対立するものではなくむしろ相補的なものだ。こうした世界観に対置されるのは「人間の側からの特殊なアプローチによって世界の運用の決まりを修正しうる、神々の世界にアプローチし得る」と考える呪術の発想である。
1-16
キリスト教はもともと、聖書の全てを字義通りに正しいと信じるものではない。(より多くの表現を整合的に受けとめられるような考え方を暫定的に採用することが信仰?)科学と宗教は部分的に矛盾を来す場合があるものの、根本的には対立するものではない。「矛盾した場合にはどちらを採用する」という一定の方針のもと認識を擦り合わせれば、それらは十分に整合的なものとなる。キリスト教徒の多数派は「科学に矛盾しない限りにおいて宗教を信じる」、福音派は「宗教に矛盾しない限りにおいて科学を信じる」という態度をとる。両者はどちらに重点を置くかが異なるだけで、極めて同型的である。また信仰には、教義を事実として意識的に信じる次元と、その宗教がもつ認識の枠組みや世界への態度を無意識的に身につけ振る舞う次元とがある。
丸山眞男によれば、宇宙の起源を説明する論理には「神が宇宙を創造する」「神が宇宙を産む」「宇宙は植物のように生成する」という3つの類型がある。
キリスト教やユダヤ教において苦しみを試練と捉えるのは、仏教の一切皆苦の思想と同じ「機能」を果たしていると感じる。
tsuzuki670 さん
キーワードで引用ノートを探す