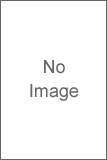四世紀の後半、諸部族の移動や攻勢の前に「ローマ人」のアイデンティティは危機に瀕し、ついに変質した。 そして、新たに登場した「ローマ」を高くかかげる思潮は、外国人嫌いを伴う、排斥の思想だった。 つまり、国家の「統合」ではなく「差別」と「排除」のイデオロギーである。 これを私は「排他的ローマ主義」と呼んだが、この思想は、軍事力で実質的に国家を支えている人々を「野蛮」と軽蔑し、「他者」として排除する偏狭な性格のものであった。 この「排他的ローマ主義」に帝国政治の担い手が乗っかって動くとき、世界を見渡す力は国家から失われてしまった。 国家は魅力と威信を失い、「尊敬されない国」へと転落していく。 (p203)
***
最盛期のローマ帝国は、担い手も領域も曖昧な存在であったにもかかわらず、一つの国家として統合され、維持されていた。 そして、その曖昧さこそが、帝国を支える要件であったのは、本書で見てきたとおりである。 そうした曖昧さを持つローマ帝国を実体あるものとしたのは「ローマ人である」という故地に由来するアイデンティティであった。 アイデンティティなるものは本来、他と区別して成立する独自性を核としている。 にもかかわらず、最盛期のローマ帝国がこのアイデンティティの下で他者を排除するような偏狭な性格の国家とならなかったのは、それが持つ歴史とその記憶ゆえであった。 ローマ帝国には、あのリヨンのクラウディウス帝演説の銅板に刻まれているように、外部から人材を得てきた歴史があり、その記憶があった。 そうした王政・共和政時代以来の国家発展の歴史を認識し記憶することにより、人々は偏狭な自己認識に陥らなかったのである。 (p205~206)
(
続きを読む)
 haruga6 さん(2013/07/21 作成)
haruga6 さん(2013/07/21 作成)