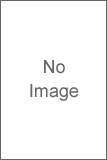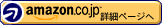『「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と叫ぶ人に訊きたい―――正義という共同幻想がもたらす本当の危機』の読書ノート作成者:masudakotaro さん
2014/06/21 作成
【第5章】
だいたいネクタイって変だ。首を巻く細長い布。実用性は何もない。防寒にも役立たない。人類が滅んだあとに地球にやってきた異星人は,大量に発見されるこの奇妙な布切れの用途について首を傾けるだろう。まさか首に巻いていたなどとはなかなか発想できないに違いない。だって意味がないからだ。
明治以降,日本が他国と結んだ同盟は,日英同盟と日独伊三国同盟くらいのはずだ。なぜなら同盟とは,「国家目標を達成するために二つ以上の国が軍事上の義務を伴った条約に基づいて提携すること」を意味する。つまり集団的自衛権が前提になる。
建前としては,日本に軍隊は存在していない。だから他国との(軍事)同盟など,論理的にはありえない。
捕虜となった彼らのほとんどは兵士ではない。村を略奪したときに捕まえた農民たちだ。だから女もいる。特に若い女性の場合は,まずは大隊長や中隊長の「慰安婦」とされ,さらにいくつかの中退に分配されて複数の兵士たちの相手をつとめ,最後には殺される。さんざんにもてあそんだ十代後半の少女を殺害してから,その大腿部をスライスして油で炒めて食べた部隊もあったという。まさしく中国の農民たちにとっては,比喩ではなく野獣の軍隊だ。
軍人らしい軍人を作るという大義名分のもとに,古年兵による初年兵への私的制裁は当たり前のように行われました。「君」とか「あなた」などの言葉を使っただけでも殴られる。足腰が立たなくなるほどに蹴られる。捕虜を銃剣で突き殺さねば自分が半殺しにされる。こうして初年兵たちは,普通なら持ち合わせているはずの感情や良識や人間性を,暴力によって根こそぎ奪われ,ただ上官の命令に反射的に服従し,命令さえあれば平気で人間を虐殺する機械に変わっていきました。だからこそ日本の軍隊は捕虜や一般市民に対して,これほどに残酷な犯罪行為を,ためらいなく行うことができたのでしょう。
人工衛星の打ち上げをミサイル発射だとアナウンスするならば,それは乱暴すぎると言わねばならない。向こうが無茶苦茶だからこちらも無茶苦茶でよいとは思わない。街場の喧嘩ではないのだ。筋は通すべきだ。どうしても「事実上はミサイルなのだ」と断言したいのなら,その理由と根拠を明示すべきだ。
でもこのままの形で風化すべきではない。なぜなら彼らがサリンを撒いた(不特定多数を殺傷しようとした)理由を,この社会はまだ解明できていない。つまり動機がわからない。しかも解明できていないとの意識を,ほとんどの人は持っていない。彼らが凶暴で凶悪だからとか,麻原からマインドコントロールされていたからなどの浅いレトリックによって,何となく納得したような気分になっている。
確かに実行犯たちが「麻原から指示を受けたからサリンを撒いた」ことは明らかだ。でもならばなぜ,麻原がそのような指示を下したのか。何を狙い何を目的にしていたのか,その理由や背景がわからない。わからないのに裁判は一審のみで終了した。早く麻原を処刑せよとの声に,司法とメディアが従属した。
麻原法廷を典型に,やるべきことの多くをこの社会はやっていない。それでは教訓どころか副作用しか残らない。こんなふうに引きずり続けるのなら,跡形もなく風化して一切を生奥から消してしまったほうがよほどいい。風化の仕方を間違えている。
こうした反体制的な作品がハリウッドの娯楽映画として当たり前のように制作されることに,アメリカの凄みと本質がある。短絡的で手前勝手で自己陶酔的などうしようもない国だけど,復元力は確かにある。それを支えるのは徹底した情報公開と,権力を監視するジャーナリズムへの国民の信頼だ。
イラク戦争終結後,アメリカを支持した国の多くも過ちを認め,イギリスのブレア政権やオーストラリアのハワード政権は国民の支持を失い,ブレアに至っては退陣してから3年後の2011年に,イラク戦争に関する独立調査委員会の公聴会で証人喚問されて,自らの判断の過ちを認めている。つまり国レベルで過ちを,しっかりと検証しようとしている。どのように風化すべきかを考えている。
でも日本では,そんな動きはまったくない。当時の政権は言うに及ばず,アメリカ支持を主張していた識者や評論家やジャーナリスト,そして多くのメディアも,自らの過ちを自己検証するどころか認めてすらいないし,責任を追求されてもいない。
だいたいネクタイって変だ。首を巻く細長い布。実用性は何もない。防寒にも役立たない。人類が滅んだあとに地球にやってきた異星人は,大量に発見されるこの奇妙な布切れの用途について首を傾けるだろう。まさか首に巻いていたなどとはなかなか発想できないに違いない。だって意味がないからだ。
明治以降,日本が他国と結んだ同盟は,日英同盟と日独伊三国同盟くらいのはずだ。なぜなら同盟とは,「国家目標を達成するために二つ以上の国が軍事上の義務を伴った条約に基づいて提携すること」を意味する。つまり集団的自衛権が前提になる。
建前としては,日本に軍隊は存在していない。だから他国との(軍事)同盟など,論理的にはありえない。
捕虜となった彼らのほとんどは兵士ではない。村を略奪したときに捕まえた農民たちだ。だから女もいる。特に若い女性の場合は,まずは大隊長や中隊長の「慰安婦」とされ,さらにいくつかの中退に分配されて複数の兵士たちの相手をつとめ,最後には殺される。さんざんにもてあそんだ十代後半の少女を殺害してから,その大腿部をスライスして油で炒めて食べた部隊もあったという。まさしく中国の農民たちにとっては,比喩ではなく野獣の軍隊だ。
軍人らしい軍人を作るという大義名分のもとに,古年兵による初年兵への私的制裁は当たり前のように行われました。「君」とか「あなた」などの言葉を使っただけでも殴られる。足腰が立たなくなるほどに蹴られる。捕虜を銃剣で突き殺さねば自分が半殺しにされる。こうして初年兵たちは,普通なら持ち合わせているはずの感情や良識や人間性を,暴力によって根こそぎ奪われ,ただ上官の命令に反射的に服従し,命令さえあれば平気で人間を虐殺する機械に変わっていきました。だからこそ日本の軍隊は捕虜や一般市民に対して,これほどに残酷な犯罪行為を,ためらいなく行うことができたのでしょう。
人工衛星の打ち上げをミサイル発射だとアナウンスするならば,それは乱暴すぎると言わねばならない。向こうが無茶苦茶だからこちらも無茶苦茶でよいとは思わない。街場の喧嘩ではないのだ。筋は通すべきだ。どうしても「事実上はミサイルなのだ」と断言したいのなら,その理由と根拠を明示すべきだ。
でもこのままの形で風化すべきではない。なぜなら彼らがサリンを撒いた(不特定多数を殺傷しようとした)理由を,この社会はまだ解明できていない。つまり動機がわからない。しかも解明できていないとの意識を,ほとんどの人は持っていない。彼らが凶暴で凶悪だからとか,麻原からマインドコントロールされていたからなどの浅いレトリックによって,何となく納得したような気分になっている。
確かに実行犯たちが「麻原から指示を受けたからサリンを撒いた」ことは明らかだ。でもならばなぜ,麻原がそのような指示を下したのか。何を狙い何を目的にしていたのか,その理由や背景がわからない。わからないのに裁判は一審のみで終了した。早く麻原を処刑せよとの声に,司法とメディアが従属した。
麻原法廷を典型に,やるべきことの多くをこの社会はやっていない。それでは教訓どころか副作用しか残らない。こんなふうに引きずり続けるのなら,跡形もなく風化して一切を生奥から消してしまったほうがよほどいい。風化の仕方を間違えている。
こうした反体制的な作品がハリウッドの娯楽映画として当たり前のように制作されることに,アメリカの凄みと本質がある。短絡的で手前勝手で自己陶酔的などうしようもない国だけど,復元力は確かにある。それを支えるのは徹底した情報公開と,権力を監視するジャーナリズムへの国民の信頼だ。
イラク戦争終結後,アメリカを支持した国の多くも過ちを認め,イギリスのブレア政権やオーストラリアのハワード政権は国民の支持を失い,ブレアに至っては退陣してから3年後の2011年に,イラク戦争に関する独立調査委員会の公聴会で証人喚問されて,自らの判断の過ちを認めている。つまり国レベルで過ちを,しっかりと検証しようとしている。どのように風化すべきかを考えている。
でも日本では,そんな動きはまったくない。当時の政権は言うに及ばず,アメリカ支持を主張していた識者や評論家やジャーナリスト,そして多くのメディアも,自らの過ちを自己検証するどころか認めてすらいないし,責任を追求されてもいない。
masudakotaro さん
キーワードで引用ノートを探す