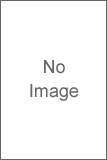「明石屋ではないか」
と、馬上の士が、声をかけた。
万吉がふりむくと、官軍の高級士官らしい人物で、長州軍制服の上に錦の陣羽織をはおっている。
「おれだ、わすれたか」
「はて」
万吉はとぼけた。このあたりが、万吉の侠客としての腹芸のひとつであろう。
「わすれてもらってはこまる。おまえに命をたすけられた長州の遠藤謹助だ」
(ああ、理屈屋の遠藤か)
むろん、万吉は馬上の士を見たとたんに思い出しているのだが、そういう顔つきをすれば万吉の男稼業がすたるであろう。
「一向に存じまへんな」
「よく顔をみろ」
と、遠藤は馬から降り、韮山笠をとって万吉に笑いかけた。
「ああ、思いだしました」
「あっははは、物おぼえのわるいやつだ。ーーところで」
と、遠藤は万吉と、万吉をとりかこんでいる松時雨らを見くらべつつ、
「ここでなにをしている」
「首」
自分の首に手をやり、
「これだす」
と、刎ねるまねをした。
「ははあ、時勢だな」
遠藤は笑いだした。以前は自分がいまの万吉の立場にあったことを思うと、時勢の変転というのはまるで芝居の回り舞台のようである。
「ほな、失礼」
と万吉が河原へおりかけると、遠藤はあわてて、待てーーといった。
「おまえを処刑すれば、長州の恥辱だ。なぜわれわれを救ったことを、この屯営の連中に言わぬ」
「わすれましたのでな」
万吉はもう芝居がかっている。
「わすれたわけでもあるまい」
「たとえ覚えていても、この場になって昔の恩を担保(かた)に命乞いをしようとは思いまへん」
「申したなあ。それでこそ任侠だ」
遠藤は万吉の縄をとかせ、あらためて屯営へ連れてゆき、座敷にあげ、この寺の小僧に命じて茶菓の接待をさせた。(
続きを読む)