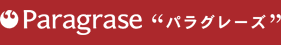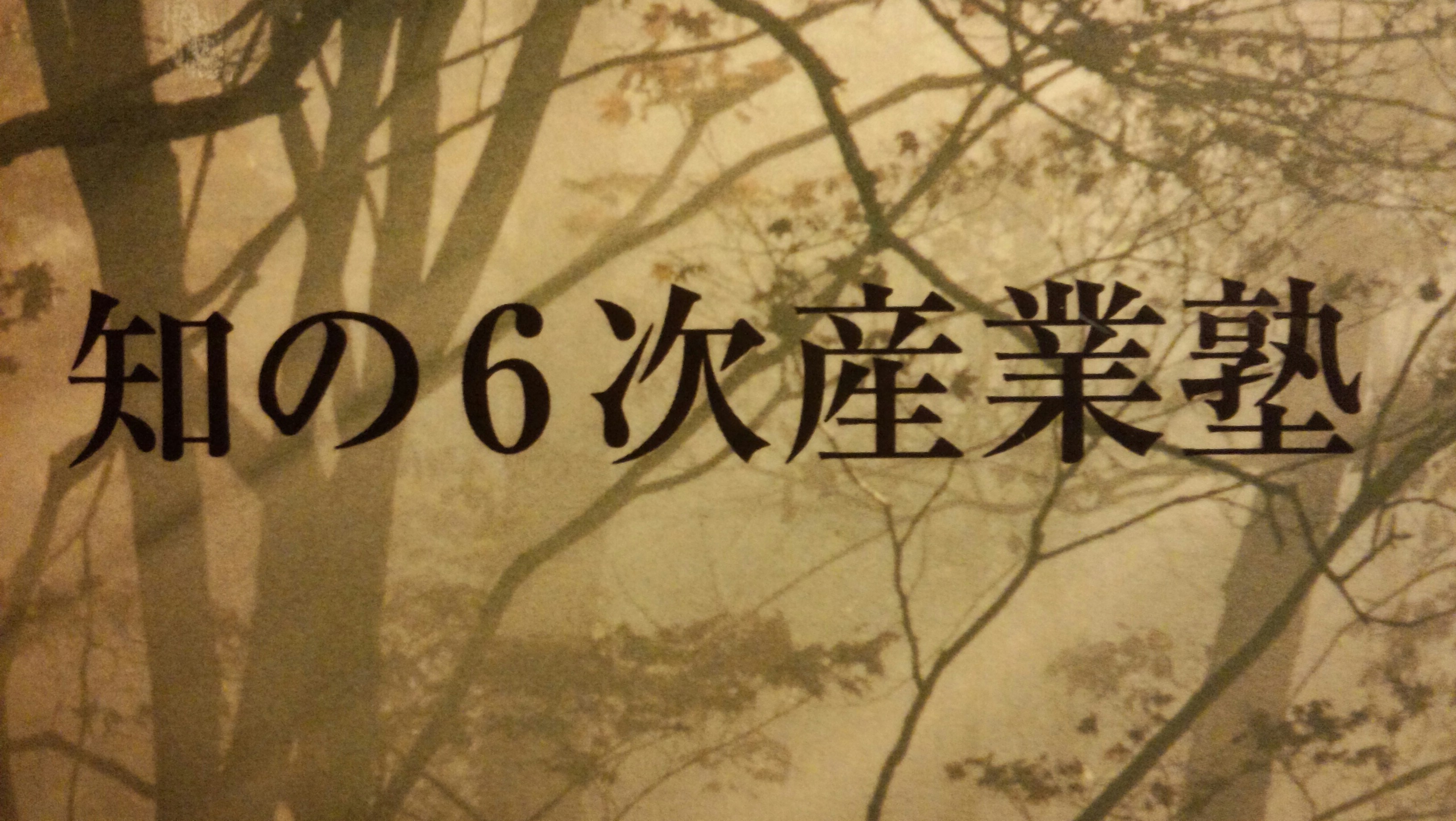選んだポイントを,プレスリリース,ウェブサイト,プレゼンテーションなど,すべてのマーケティング資料で繰り返し同じ形で取り上げる。
救世主的な目的意識を持つ。
ジョブズが語るとき,そこには情熱があり,勢いがあり,活気がある。
「大好きなことを見つけてほしい。仕事というのは人生のかなり大きな部分を占めるわけだけど,本当に満足するには,すごい仕事だと信じることをするしか方法がない。そして,すごい仕事をするには,自分がすることを大好きになるしか方法がない。まだ見つからないなら,探し続けてほしい。あきらめちゃいけない。」
自分にとって何が生きる目的なのだろうか。それを自覚し,全身全霊で表現しよう。
偉大なプレゼンターは情熱的なものだが,それは自らの心に従って行動するからだ。偉大なプレゼンターにとって会話とは,その情熱を他人と分かち合う方法なのだ。
自分のサービス,製品,会社,主義主張に対する情熱がなければ,テクニックなど何の役にも立たない。コミュニケーションの極意は,情熱を心底傾けられるものを見つけること。そして,見つかるのは「モノ」ではなく,モノが顧客の暮らしをどう改善するのか,である。
見つかるのは「モノ」ではなく,モノが顧客の暮らしをどう改善するのか,であることが多い。自分の心を探り,情熱を注げるものを見つけること。「私が売り込もうとしているものは,本当のところ何なのだ」と自問するのだ。それは「モノ」ではなく,モノが顧客の暮らしをどう改善するのか,のはずだ。売っているのは,よりよい暮らしという夢なのだ。本物の情熱を自覚できたら,それをみんなに楽しく伝える。
自分だけの「パッションステートメント」を作る。なぜ心から真剣にそうしているのか,その理由を1文にまとめ,売り込む相手に伝えるのだ。一緒に説明した会社のミッションは忘れられても,パッションステートメントは相手の心に残るはずだ。
聴衆に感銘を与えられるスピーカーになりたいが今の仕事がどうしても好きになれない場合,仕事を帰ることを考えるべきだ。成功を収めたリーダー,数千人から話しを聞いた結果,分かったことがある。仕事が大嫌いでも大儲けは可能だが,聴衆に感銘を与えるコミュニケーターには絶対になれない。情熱,つまり,世の中をよくしたいという熱意が違いを生むのだ。
ツイッターのようなデッドラインを作る。
ヘッドラインと呼ばれる短い文章で製品を的確に表現し,ジョブズが,新製品にあいまいな部分が残らないようにしたいのだ。
ジョブズは,その製品にも必ずといっていいほど1文で評した概要を用意する。
会社や製品,サービスを一言で表せるプレゼンターは少ない。計画のごく早い段階でヘッドラインを用意しなければ,一貫したメッセージを発信することはまず無理である。ヘッドラインを核にプレゼンテーションを作り上げるべきなのだ。
記憶によく残るヘッドラインの3つの条件。①簡潔,②具体的,③利用者にとってのメリットが分かる。
会社,製品,サービスなどのビジョンを1文で表すヘッドラインを作ること。効果的なヘッドラインとなるポイントは,簡潔であること(70文字以下),具体的であること,受けて自身のメリットを示すことだ。
プレゼンテーション,スライド,パンフレット,資料,プレスリリース,ウェブサイトなどのマーケティング資料および会話で,同じヘッドラインを繰り返し用いること。
ヘッドラインとは,よりよい未来というビジョンを聴衆に提案するものという点を忘れないこと。あなたにとってのよい未来ではない。聞き手にとってのよい未来だ。
ロードマップを描く。
道しるべとなる言葉をしゃべりに混ぜるとそれがロードマップとなり,ストーリーを追いやすくなる。
3点で構成されたロードマップをしゃべりに組み込むと,聞き手が迷子にならないのだ。
必ず3点か4点にまとめてポイントを紹介したあと,最初のポイントから順番に詳しく説明し,最後にそれぞれのポイントをまとめるのだ。こうするだけで,提供する情報を聴衆が確実に覚えてくれる。
紹介する製品,サービス,会社,構想について,聴衆に知ってほしいと思うポイントをすべてリストアップする。
このリストを分類し,主要メッセージが3つとなるまで絞り込む。この3つのグループが,売り込みやプレゼンテーションのロードマップとなる。
3つのキーメッセージ,それぞれについて,効果を高める部品を用意する。体験談,事実,実例,アナロジー,メタファー,推薦の言葉などだ。
(
続きを読む)
 h_nagashima さん(2012/10/31 作成)
h_nagashima さん(2012/10/31 作成)