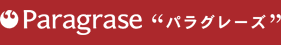【第八講 無自覚の「意志」】
行動,特に無意識的で反射的な行動の変化が,認知あるいは言語のレベルでの方向の再整理に先立つ。
とっさの反応はできるが,あらためて問われたり,自問すると混乱してしまう。
本人は刺激に気づいていないのに身体が勝手に反応する。たとえば同時し失認といって,視野の中の個々のものはわかるのに全体の関係が認知できない症状を持つ患者。そういう患者でも,本人は視覚刺激の存在に自覚的には気づいていないのに,眼球はその方向へ動いていた。
線分の方向を自覚的に検知し,言語で報告することができなかったのに,カードによるスロット課題の遂行となると,たちまち方向の情報を活用できる。
感覚系と運動系をつなぐ神経経路はひとつではなく,いくつかの異なるレベルがある。そのうちの低次のものは自覚できず,高次のものだけが自覚化できる。
姿勢・運動制御の経路は昆虫や鳥や哺乳類でも比較的下等な種でむしろ優勢であり,これに対して物体認知の経路は,サルやヒトなど高等な動物ではじめて優勢となる神経メカニズム。姿勢・運動制御の経路がおおむね無自覚的あるいは潜在的であり,物体認知の経路がおおむね自覚的あるいは顕在的なのは,むしろ当然。
自発的意志とはいったい何なのか。自由意志は自覚的であり,意識的である。つまり「意志」は通常顕在的メンタル・プロセスの典型的な例とみなされる。
自分の「意志」を報告できたし,その前後に起こった理由づけや思考や怒りなどの情動も含めて,すべて自覚でき,言語によって報告できたように見える。
行為はたいていの場合手を動かしたり,足を動かしたりといった筋肉運動を伴っており,その生理学的機構はかなりのところまで解明されている。この場合の「機構」というのは,徹頭徹尾ものの世界の因果関係で記述されている。この記述は完全に機械論的記述であり,ロボットやサイボーグでも,人間でも,本質的には同じ過程であると考えられている。「自由意志」はどこで蒸発してしまったのか。
意図的な行動のひとつの特徴は,それがなにがしかの意味で「目的にかなう(合目的的である)」ということ。意識的な心的過程の最たるものは自発的意志であり,その有力な特徴が合目的性なので,この合目的的な行動のメカニズムということが,生理学上の大きな関心事となる。
条件づけとはすなわち環境からの刺激に対して適合的な行動を学習することにほかならず,適合的とは合目的的と言い換えることができる。
オペラント条件づけ=道具的条件づけ
古典的条件づけ
はじめは反応を引き起こすことができなかった条件刺激が,より強い無条件刺激と繰り返しペアで呈示されることによって,単独でも反射を引き起こすようになる。合目的的で環境に適応的な反応の仕方を学んだ。
条件づけそのものを可能にするメカニズムと,その効果を貯えるメカニズムは別である。古典的条件づけの場合には,条件づけメカニズムそのものは頭部神経節にあるが,貯蔵する機能は胸部や腹部の神経節にも分散している。
オペラント条件づけは,はじめから頭部のない昆虫でも成立する。
古典的条件づけのほうは,頭部神経節なしでは成立しないが,いったん成立して十分に固定されれば,頭部がなくなっても学習の効果は残る。
断頭カエルでも,普通のカエルと同じように,右肢を固定してから右側の背中に酸を垂らすと,左肢で掻く。→目的にかなう行動(随意運動)は脊髄レベルで組織化され得る。
除脳犬(無大脳犬):大脳のない犬は,刺激を与えられない限り眠っているように見えた。しかし,大きな音を立てると目覚め,痛み刺激によってうなり,立たせると自分の足で歩き,口に食物を入れると飲み込んだ。日差しの入る窓辺へ行って寝そべり,気持ちよさそうにうたた寝さえした。
除脳犬は駐立姿勢(四つ足で立った姿勢)を保ち,前へ引っ張れば前肢で支えて,後ろへ引っ張れば後肢で支えて抵抗するというように,大脳のある普通の犬と同じ行動をとった。(
続きを読む)
 yo-ko さん(2014/08/15 作成)
yo-ko さん(2014/08/15 作成)