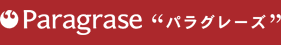【第二講 悲しいのはどうしてか?】
自己に対する内的な知識はきわめて不完全である。それは無意識的な推論によって補われているものであり,極言すれば自分とはもうひとりの他人であるにすぎない。
情動二要因理論。
私たちは悲しいからなくのか,泣くから悲しいのか。
ジェームズ-ランゲ説:泣くから悲しいのだと主張する立場。「情動の末梢説」。
教示や演技など別の理由で表情を作った場合ですら,主観的に経験される情動は,予想外に大きく作られた方向に引きずられる。
情動経験は感覚刺激に依存する。しかしまた顔筋の変化=表情と情動経験の間には連合-相関関係があり,この関係は表情の変化が教示や演技による場合にも変わらない。つまり感覚刺激なしに教示や演技によって表情を作った場合ですら,このような強い連合関係のために,情動の経験が想い起こされてしまう。
ジェームズ主義では,表情を作ることがむしろ先立ち,それによって逆に主観的経験としての情動が形成されるという筋道。
との説も,日常感覚的には承認しがたい時間的生起順序・因果関係している。つまりこれらの説では,身体の生理的変化が先で,次にこれが原因で情動が生じるというのだ。しかし私たちの日常的経験は,これとは逆のように思える。
時間的生起順序・因果関係を承認しにくいのは,これらの理論が,本人も自覚的にアクセスできない意識化の過程の存在を示唆しているから。「身体的過程→潜在的認知過程→自覚的情動経験」という関係が重要。
情動二要因理論の大前提=情動による生理的喚起=興奮状態は,情動の種類(喜び,怒り,悲しみなど)にかかわらず共通である。
情動二要因理論では,情動経験について二段階のシナリオを考える。このふたつが満たされてはじめて情動認知が成立する。
1. 生理的な喚起(興奮)状態の認知。
2. 情動ラベルづけ(喚起状態の推定,あるいは原因への帰属)。
人は自分の主観的な情動の経験を「決定する」ために,①自分の内的状態と,②その状態が生じている環境とを評価する。
つり橋に対する恐怖からの緊張と性的興奮との間には,生理的には曖昧な区別しかない。そこで状況の認知(美人に声をかけられた)から,興奮状態を作り出した原因を「謝って」そこ(魅力的な異性との出会い)に帰してしまう。この帰すること=帰属によって,性的興奮度や,初めて出会った異性に対する関心の度合いがいっそう高まったものと想像される。
実際の生理的興奮が起こっていなくても,「自分は今生理的に興奮している」という認知さえあれば,常道のラベルづけをおこない,情動認知が起こりうる。生理的興奮そのものが情動経験のための必要条件なのではなく,生理的興奮の自己認知が必要条件。
興奮条件ではむしろよく眠れたのに,リラックス条件ではなかなか眠りにつけない。
就寝時に強く自覚される生理的興奮を100パーセント薬のせいにできる。そのため生理的興奮の情動へのラベルづけが起こりにくく,情動認知が低くなる結果,不眠症状が軽くなるのではないかと考えられる。これに対してリラックス条件では,「鎮静剤を飲んだのに」依然として興奮を自覚するので,それをいつもより高く推測し,ふだんより強い情動認知をする。その結果,不眠はむしろひどくなってしまう。
本人が自覚できず,したがって申し立てることもできないが,行動には反映されているような,無意識的な認知過程。そういうプロセスの存在を示している。
情動二要因論の骨子:
1.生理的興奮そのものは情動の種類に関わらず,案外類似している。
2.感情のように一見生理学的要因に直結しているように見えるものでさえ,案外無意識的な認知過程(たとえばラベルづけ)の結果である一面が大きい。
3.行動に顕れる無自覚の認知過程と,言語報告に現れる無意識的な過程とは別物である可能性がある。人は自分の気持ち・行動のほんとうの理由を案外知らない。そこではたらく過程は非生理的できわめて認知的でありながら,それでいて意識的・自覚的ではない。意識的過程は結局,意識的過程をしか(直接的には)知り得ない。
(
続きを読む)
 yo-ko さん(2015/10/11 作成)
yo-ko さん(2015/10/11 作成)