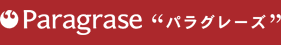・忍耐力を鍛えるために
1 目標、願望の明確化
2 強いエンスージアズム(熱意)を伴った目標実現意欲
3 自信
4 計画の明確化
5 正確な知識
6 マスターマインド
7 意思の力
8 習慣
・ウィークポイントを乗り越える
1 自分が何を望んでいるのかわからず、説明もできないこと。
2 理由があろうとなかろうと仕事を翌日に延ばすこと(もっともらしい言い訳をつけて)。
3 知識欲、勉強意欲が欠けていること。
4 優柔不断。いつも正面から対決することを避け、すべてにわたって責任転嫁すること(これにももっともらしい言い訳がある)。
5 明確な計画を立てることをせず、口実をつくっては言い逃れをすること。
6 自己満足。この病気は治しようがない。この病気にかかっている人には、明日への希望はない。
7 無関心。問題が生じたときに、直面して闘おうとはせず、すぐ安易に妥協しようとする、その態度の根本にあるのはこの無関心である。
8 他人の失敗は厳しく責め立てるが、自分の失敗はなかなか認めようとしない。
9 動機づけをしなかったことからくる熱意の弱さ。またその弱さを原因とする怠け癖。
10 最初の失敗で簡単に挫けてしまうこと。
11 ずさんな計画。目標や願望を紙に書こうとしないため、分析も反省もできない。
12 目の前にアイディアがひらめいても、チャンスが現れても、手を伸ばしてつかまえようとしない怠惰な性格。
13 夢想するだけで何もしないこと。
14 豊かになるために苦労するくらいなら貧乏なままでもいいという態度。このような人は「こうなりたい」「こうしたい」「これが欲しい」という強い意欲が欠けているのだ。
15 自ら汗を流そうとはせず、ギャンブルや投機などで近道を探して儲けようとすること。
16 批判を気にする。他人の考えや行動、発言が気になり、批判されることばかりを恐れる結果、行動を起こさない。これは、このリストの中でも最大の敵である。なぜなら、これは目には見えないが、誰もが潜在意識の中に持っているものだからだ。
・忍耐力を身につける4つのステップ
1 燃えるような熱意に支えられた明確な願望や目標を持つこと。
2 明確な計画を立て、それを着実に実行していくこと。
3 親戚、友人、周囲の人たちの否定的な、あるいは意気消沈させるような意見をきっぱり拒絶すること。
4 目標と計画に賛成し、激励してくれるような人を1人、あるいはそれ以上を友人にすること(マスターマインド)。
・「人生には、さまざまな境遇の巡り合わせが絶え間なく起こっているものだ」
・エンスージアズムはこうして持つことができる
1 大きな声で話をすること。
2 早口で話すこと。
3 強調すること。
4 間をとること。
5 声に微笑みを込めること。
・計画に熱意を持つ6つの秘訣
1 熱心で楽観的な人々と付き合うこと。
2 まず財政的な成功を築き上げるために働くこと。
3 成功のノウハウをマスターして、日常の生活に適用すること。
4 健康に注意すること。
5 PMA(積極的心構え)を維持すること。
6 他人の手助けをすること。
・「失敗や逆境の中には、すべてそれ相応かそれ以上の大きな利益の種子が含まれている。」
(
続きを読む)
 yo-ko さん(2014/07/05 作成)
yo-ko さん(2014/07/05 作成)