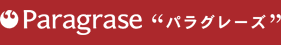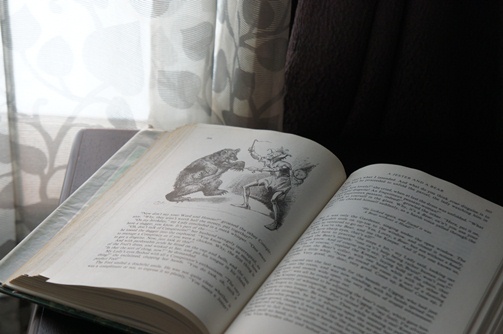『文学・評論』関連の読書ノートリスト
- 全 233 件中 171 〜 180 件の引用ノートを表示
- 並び替え: 新着順 / 人気順
-
読書家の新技術 (朝日文庫) の引用ノート
呉 智英 / 朝日新聞社
p.37 だが、そもそも、公認された知の集合・知の世界=教養という時の「公認」には、保守的なものも進歩的なものもともに含まれる。進歩的なものは、保守派にとっても、進歩的なるものとして諒解可能なのである。共産主義は、反共主義者にとって、共産主義なるものとして諒解可能なのである。公認の配分という程度の差こそあれ、進歩も保守も公認教養の中に含まれているのだ。(続きを読む) BafanaBafana さん(2015/01/20 作成)
BafanaBafana さん(2015/01/20 作成)